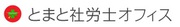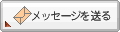2017年03月09日
地域支え合いシンポジウムの様子@糸満市社会福祉協議会
地域支え合いシンポジウム
~誰もが安心して暮らすためにできることは~
糸満市社会福祉センターにて開催されたシンポジウムに参加しました。
「いま、本当に必要な支援とは?~子供の貧困から考える生活困窮者の自立支援~」と題した
NPO法人沖縄青少年自立援助センターちゅらゆいの代表理事金城隆一氏の基調講演についてお伝えします。

生活困窮者の不登校についての話が印象的でした。
怠けて学校に行かないんじゃないの?と思われることもありますが
その根底には自己肯定感の薄さがありました。
土台という言葉がよく使われていましたが、
個人課題(自己肯定感、対人関係力、環境調査)への支援を抜きに
トレーニング(学習支援、就労支援、生活訓練)を実施しても効果が薄く、
支援が長続きしないのだそうです。
「自分なんか」という自己否定感
金城氏は那覇市の子供の居場所kukulu(くくる)での実践事例を紹介してくださいました。
不登校だったやす君の言葉すべてから土台の大切さが伝わってきましたよ。
不登校である状況だけに目を向けて、自分の存在が認められず、
背景にある問題に目を向けなければ、状況は改善しないことが多いのです。
学習支援、就労支援、生活訓練も大切ですが、
その前に自己肯定感。自分が自分でいられることが大事なんですね。
基調講演の後は糸満市の取組として
糸満市社協 くらしのサポートきづき 小那覇良一氏
糸満市西崎太陽児童センター 金城文子氏
による実践報告があり、糸満市の状況やどのような支援がされているのかを
知ることができました。
さて、例えば不登校の子どもに出会ったとき、どのように接すればいいのでしょう。
自己肯定感を高めるには?
~誰もが安心して暮らすためにできることは~
糸満市社会福祉センターにて開催されたシンポジウムに参加しました。
「いま、本当に必要な支援とは?~子供の貧困から考える生活困窮者の自立支援~」と題した
NPO法人沖縄青少年自立援助センターちゅらゆいの代表理事金城隆一氏の基調講演についてお伝えします。

生活困窮者の不登校についての話が印象的でした。
怠けて学校に行かないんじゃないの?と思われることもありますが
その根底には自己肯定感の薄さがありました。
土台という言葉がよく使われていましたが、
個人課題(自己肯定感、対人関係力、環境調査)への支援を抜きに
トレーニング(学習支援、就労支援、生活訓練)を実施しても効果が薄く、
支援が長続きしないのだそうです。
「自分なんか」という自己否定感
金城氏は那覇市の子供の居場所kukulu(くくる)での実践事例を紹介してくださいました。
不登校だったやす君の言葉すべてから土台の大切さが伝わってきましたよ。
不登校である状況だけに目を向けて、自分の存在が認められず、
背景にある問題に目を向けなければ、状況は改善しないことが多いのです。
学習支援、就労支援、生活訓練も大切ですが、
その前に自己肯定感。自分が自分でいられることが大事なんですね。
基調講演の後は糸満市の取組として
糸満市社協 くらしのサポートきづき 小那覇良一氏
糸満市西崎太陽児童センター 金城文子氏
による実践報告があり、糸満市の状況やどのような支援がされているのかを
知ることができました。
さて、例えば不登校の子どもに出会ったとき、どのように接すればいいのでしょう。
自己肯定感を高めるには?
@あいこ
Posted by まちセン*糸満市市民活動支援センター at 18:00│Comments(0)
│保健・医療・福祉
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。





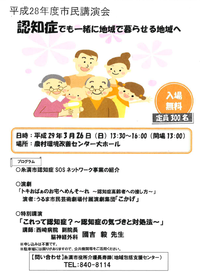


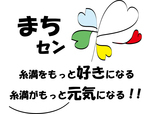








.png)